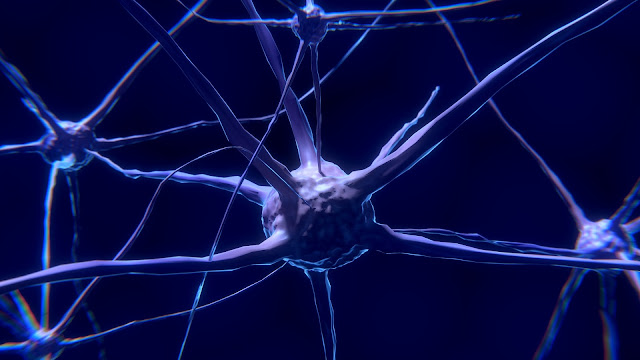アンドロイドサイエンスとアニマルライツ運動: そこにアナロジーはあるのか?
アンドロイドサイエンスとアニマルライツ運動:
そこにアナロジーはあるのか?
これは、David J. Calverleyによる論文『Android Science and the Animal Rights Movement: Are There Analogies?』の要約と抜粋である。
『ロボット倫理:反種差別主義とアンチナタリズムの観点から』において、この記事の要点をより簡潔な形で引用しているため、そちらもお勧めさせてもらう。
注意事項:
- 元論文内の引用を二重に引用する場合にややこしくなるため、元論文からの引用はインデントを変えず、文字の色を青色にして区別する。文字色が区別されない形式で閲覧している場合や、その他なんらかの理由で色の識別が困難な方は注意してほしい
- このブログ記事では、特に断りがない限り、「ヒトでない動物」のことを、「動物」と表記する。
- 参考文献は、元論文をあたってほしい。
Android Science and the Animal Rights Movement:
Are There Analogies?
David J. Calverley
Abstractはそのまま引用する:
Abstract
アンドロイドが人間のように課題を実行し、行動する日はすでに到来している。しかし、今のところ、これらの人工物を、我々の利益や娯楽のために利用する所有物以外の何かと見る準備をしているものはいない。システムがより洗練され、工学者が「意識的な」マシンを構築するよりせつなる努力をするにつれ、より多くの道徳的、倫理的、法的問題が生じる可能性があるだろう。動物の権利(アニマルライツ)運動に照らし合わせれば、適切な度合いの複雑さを考えると、アンドロイドも一定レベルの道徳的地位に値する可能性があることを示唆するアナロジーを描くことができる。しかし、アンドロイドが法的な人となる可能性があると主張するためには、他にも必要なものがある。つまり、アナロジーは完全なものではない。類似点にもかかわらず、動物とアンドロイドとの間には単なる身体性よりも深いレベルで著しい差がある。これらの類似点と相違点を同定することは、究極的には人間意識という概念をどう理解するかに依存するかもしれない。さらに、動物とアンドロイドを比較することによって、我々の意識が我々の権利概念にどのように影響するかを理解し始めることにもなるかもしれない。また、ある道徳的懸念の点は、開発プロセスのかなり早い時期に訪れるかもしれないことが示唆され、そうなった場合、もし研究者が理解しなければ、予期せぬ結果をもたらす可能性がある。このリスクに気づかなければ、アンドロイド科学の発展を妨げる反応を引き起こす可能性もある。
Introduction
導入でまず初めに語られるのは、権利の話を巡る状況である、
(議論を)始める前に、権利という用語と概念について予備的なコメントをしておく価値がある
ある行為や方針が良いことであったり悪いことであったり、正しいことであったり間違ったことであったり、道徳的であったり非道徳的であったりした場合に、我々の生活の中で生じる様々な状況を分析することを試みる方法は他にも多くあるが、現在の西洋世界では、その問題が個々人に関するものであるのか、個々人とコミュニティの間のものなのか、あるいは場合によってはコミュニティ全体と別のコミュニティの関係を含むものであるのかにも関わらず、権利について語ることが道徳的問題を定式化する最も一般的な方法の一つとなっている(Werhane, 1985)。
権利についての話は、混同や、場合によっては党派的な理由による意図的な歪曲に満ちているが、依然として「日常的な政治的言説の通貨となっている」(Waldron, 1988)
続いて指摘されるのは、しばしば「道徳的権利」と「法的権利」の区別が無視されているということである。
法的な人の古典的な定式は、「権利」の対象となるもの、すなわちそれは財産を持つことができ、訴訟を起こし起こされる能力を持つものというものである。これは、非生物が、限定された目的のために法的な人になれないという意味ではない(Stones, 1974)。しかし、対象が知性や意志を持たない限り、法的な人という用語はフィクションである(Gray, 1909)。この問題を掘り下げることはこの論文の範囲を超えるが、しばしば挑戦を受けるこの古典的な見方は、少なくとも一つの概念的な出発点を与えてくれる。
また、法と道徳の関係について、大きく二つの流れがあることが簡単に紹介される。
一つ目は、ベンサムの思想から導かれ、後に彼の後継者であるジョン・オースティンによって発展させられた法実証主義(legal positivism)であり、法はその力を主権者から導き出すものであり、また適切な制御構造によって実行される主権者の意志の表現であるというものである。権利はこの見方では、現代の法実証主義者ハンス・ケルゼン(Hans Kelsen, 1967)および(Richard Tur, 1987)による表現では、何であれ法律がそう主張するものであり、道徳など、他のいかなる内容とも独立である。
従って、この見方にはいかなる人間特性(例えば、理性や内省の能力など)と法的人間性の間にも関係がある必要はない。さらに言えば、人(person)を構成するのに要求される知性の最小閾値も存在しない。ひとたび法的人間性が明確なものとなれば、人(person)も同様に明確になるのである。現代の法的人間性は時間や空間に渡る保持的性質を欠いている。その発端や終点さえも認識が容易ではない。むしろ、法的人間性は、法的目的や司法権に加え、その内容が年齢、性別、精神的能力(すべて、自然概念とみなされる)などの因子に依存する権利や義務の集まりとみなされるようなものである(Davis and Naffeine, 2001)。
つまり、法実証主義は、法を道徳などとは切り離して考え、法律がそうだと言えばそうなのだ、という見方である。もう一つの見方は以下のように説明される:
この実証主義的(positiveな)立場とは対照的な自然法、あるいは自然権的見方は、法の外にあって権利を生じさせる独立な因子が存在しているという信念を前提にしている。
...これは、改めて過度な単純化のリスクを負えば、権利所有者は、その地位が所有物かひと(person)のどちらかであるという観点から決定される。宗教的自然権の場合、人間の権利は神の創造という地位から導かれる。より世俗的な見方では、その権利は人(person)であるとか、理性的行為を行う存在である道徳的存在であるとかいう地位から導かれる。この理性的行為者という概念こそ、西洋的な法の伝統に浸透してきたものであり、人間を動物から区別するものである。アンドロイド科学が発展することによって、究極的にはアンドロイドがこの分断された立場のどちらに置かれるのかを決定することが要求されるだろう。
Animal Rights
この節では、ヒトでない動物について見方がどう移り変わってきたかが概観される。簡単にまとめると次のような内容である:
- ユダヤ-キリスト教的伝統は、動物はヒトが支配すべき対象ととらえてきた長い歴史があり、未だにカソリック協会は、ヒトと動物には魂の有無の違いがあるという見方を維持している。
- デカルトなどは動物を機械とみなし、物と同等の道徳的重要性しか持たないとした。そして彼は、言語が人と動物を分けるものであるとも考えていた。しかし、現代では動物もある種の言語を用いると考えられている。
- カントもまた、ヒトと動物の間に大きな違いがあるという見方を抱いていた。彼は動物への配慮は、人間に対する義務から間接的に生じるだけのものであると主張している。
- それらとは対比的な見方を導入した人物がジェレミー・ベンサムである。
- カントの間接的義務という見方とは対照的に、ベンサムは動物たち自身を、配慮に値する道徳的主体とみなした。
- ベンサムが、自然権などというものは存在しないという彼の信念にも関わらず、そのような見解を抱いていたということは興味深いことである。
- ただし、ベンサムは目的なく動物に苦しみを与えるというようなことしか考慮していなかったなどの指摘もある。
- このような批判はあれど、ベンサムの見解は、人間に関する考慮ではなく、動物の内在的特性だけを理由に、動物への道徳的配慮を示した最初の見解の一つであった。
- また、ベンサムは他のものよりもさらに進んで、「平等な配慮の原理」の下で、動物たちを扱うべきという主張も行った。
- ピーター・シンガーの1975年の著書『動物の解放』以来、動物が「権利」を持つかどうかの議論が盛んになった。
- ただし、シンガーは動物も、道徳的配慮に値するに十分な「利害」を持つという概念に基づいた功利主義的な見方から議論しており、「権利」という言葉は用いていない。
- 対照的にトム・リーガンは、動物も生の主体であり、それにより内在的な価値を持つという見方から、明示的に権利を主張した。
ベンサムの「平等な配慮」という考えは、現代の言葉で表現すると次の通りである:
実践的レベルでは、重要なことに、動物の平等な配慮によって、人類の利益という名の下で行われている動物の利益の日常的踏みつぶしのほとんどは除外されるだろう。平等な配慮は他の異なる倫理理論と調和するが、それは――動物にまで拡張されたなら――動物たちを我々が利用するための資源と見るあらゆる見方とも調和しない。平等な配慮はもしかしたら人間のための動物利用の一部となら調和するかもしれない(そして恐らくは人間の利用とさえも調和する。徴兵制などを考えてみればいい)。しかし、不平等な配慮は、動物と人間は、上に立つものが下にいるものを自身の生活を向上させるための資源とみなすヒエラルキーの中にいるという根本的な道徳的地位の違いがあるということを含意している(DeGrazia, 1996)。
ゲイリー・フランシオンは、動物の基本的権利とは、他者に物として利用されない権利であるとしている。
これは、(ベンサムと対比し)一人の人間は他のどんな人間とも道徳的なレベルで等価であるが、必ずしもあらゆる目的においてではない、ということを意味する平等な内在的価値(Equal Inherent Value)の概念と同一視される。「人類が正確にどんな権利を持っているかということには大きな意見の不一致があるだろうが、我々は現在全ての人間を、完全に他者の目的のための道具として利用されることがない権利を持つ存在とみなしていることは明らかだろう。これは基本的な権利の一つであり、他の全ての権利と異なるものである。他のあらゆる権利を享受するために必要な前提条件となる、法に先行する権利なのである」(Francione, 2000)。この定式化の方法は本質的にはカント的であるが、この文脈に含まれる意味には大きな違いがあることは興味深い。
権利を持つために要求される特性は、論者によっていくつか挙げられている。しかし
フランシオンの見方では、認識的経験を持つ能力があるという意味での知覚、特に痛みと喜びが、動物種の道徳的保護という防具一式を生み出すのに十分である。しかしこれが意味するのは、動物は道徳的対象以上の何かではないことを意味するのだと示唆され、道徳的主体としての地位は持たないことを意味している。これによって私が意味してるのは、十分食事を与えられたネコが、食事のためにではなく、単なる「喜び」のためにネズミを殺すことを、殺人と同等の罪として咎めるのは馬鹿げているということである。
...従って、見てわかる通り、アニマルライツに関する議論は動物は単なる所有物であるから内在的価値を持たないという概念から、道徳的選択の際に考慮され重みづけされる利害を持つ資格のある存在であるという見方、あるいは最終的には、生の主体であり物よりも上にあるものだという理由のみから、完全な道徳的配慮が与えられる存在であるという見方まで広がっている。
そして、この節は以下のように締めくくられる
現在では、動物たちは権利や、あるいは我々が彼らを道徳的重みを帰属させるに十分な利害を持ち、単純に人間の利用や利益のための商品として扱われてはいけないものと見られるようになっている。この帰属に要求される決定的な具体的特性やその範囲は未だ明確には確立されていない。一度それが確立されれば、それらは動物たちを道徳的な人として扱うことに繋がる。しかし、必ずしも彼らを法的な人と見る必要はない。
The Analogy
ここでの私の課題は、同様の仮定のセットを明確化し、アンドロイドに適用することができるのかを検討することである。私が提唱するアナロジーは以下のように表現できる。動物は過去には所有物とみなされていた。彼らは所有物であり、不滅の魂も持っていないのだからという理由で、人間が搾取してよいものであった。現代科学の結果として、動物たちは全体として様々な程度で、岩や木などの非動物的な物より上だがヒトよりは下の何かとなる特性を持っていることが示されてきた。
これが、アンドロイドの発展とどのようなアナロジーがあるかは明らかだろう。しかし、当然アンドロイドと動物には違いもある。一つは
人間の直接の干渉から自由な形で生まれ発達する動物と異なり、アンドロイドは定義からして、始めは人間によって生み出されるものだということ。
一方でこの差異はむしろ、アンドロイドの方が人間に近い存在になりうる理由でもあることが指摘される。
もしアンドロイドにはなんらかの因子が欠けており、ある因子がある種の要求や地位を持つことへの反論になる場合、その欠けている何かを設計者によって付加されることができる。
これらの差異を考慮しつつ、以下そのアナロジーについてより詳しく検討される。
Androids
動物とアンドロイドの間の差異は、少なくとも二つの基本的なレベルで顕在化する。
一つ目のレベルは、自律性の有無である。動物は自律性を持っているが、人工的なアンドロイドはそれを欠いているため、道徳的配慮を与えるのは困難だと人々は考えるだろう、ということである。
自律性の問題で生じる基本的な問題は、それなくして、権利や義務をなんらかの有意味な形で帰属させることが困難であることだ。もしアンドロイドが、アシモフのよく知られたロボット工学原則(Asimov, 1950)のような生得的で予め決定された拘束に縛られていたら、殆どの観察者は、真の意味で自由な選択ではないと主張するだろう。決定論や自由意志についての問いもまた、この論文の範囲を超えているが、人間でさえ、この意味で自由ではないと主張するものもいることを指摘しておけば十分だろう。
しかし、著者はこの問題は回避可能であると考えている:
別のところで提示したように、理論的にはアンドロイドはこの問題を回避するようデザインされ、法的目的のために自律的になることができる。
二つ目として挙げられるのは、原理的にはアンドロイドは人間と同じ意識や他の特性を持ちうることだ。
意識とは何か、そしてどんな特性が人間の中で意識を構成するのか、ということは、心の哲学の議論の主要な主題の一つである。しかし、ひとたび「動物」から「人間」を区別するそれらの特性が特定されたと仮定したならば、アンドロイドをそのギャップの橋渡しをするようデザインできる可能性もある。そうすれば、これがアンドロイドを動物に関するカテゴリとは別のカテゴリに置くことになることがわかる。
続いて、より明確な議論の理解のため、権利保有者という語について検討がなされる。
法理論は歴史的に人と財産の間に区別をしてきたが、暗に人(person)は人間(human)と等価であるという理解が伴っていた。最近までは、よりその正確な区別をする必要はなかった。ストローソン(Strawson, 1959)とエアーズ(Ayers, 1963)
による異なる意見の表明以来、人間と人の概念ははるかに明確さを落としている。人間とは区別されるが、それでも説得力を持つ権利保有者のカテゴリを定義するために、
過去に行われてきたように、「フィクション」の形式に訴えることができる。この提案は多くの議論の対象となるものだが、少なくとも、フィクションが利用されている一般的に受容されている例の一つは、「ホモサピエンス」という種の存在と、人としての企業という法的概念の比較によって示せるだろう。
つまり、近年まで法的な人と人間の区別の必要性はさほど考慮されてこなかったが、それでも法的な人と人間はこれまでも同一のものではなく、それは法人という概念を考えてみればわかるだろうということだ。
また法的に人である人間の条件も明確ではないことが指摘される:
例えば、現在米国で展開されている生命の神聖さを巡る議論の中で、人間の胎児が受精の時点で人となるのか、それとも成長のより遅い時点でなるのかという問いについて、真剣な議論がなされている。同様の問いは人生の終わりにも付随する。すなわち、遷延性植物状態にある人間は、遺伝的なレベルでは人間でありながら、法的な人の地位を失うのか、というものである。同様に、子供や知的障害者は、彼らは明らかに人間であるにもかかわらず、一部の目的において人として扱われるものの、あらゆる目的においてではない。
つまり、このように、生物学的に人間であるからと言って自動的に法的な人とみなされるわけではないし、法的な人とみなされる場合も、その特性によって与えられる権利や要求される義務に違いが生じるということがわかる。
このような議論から、動物にも権利が与えられるべきであるという議論がうまれているわけであるが
この点を次のレベルの抽象度で考えてみると、意図的に設計されたのであれば、このようなアンドロイドが単なる所有物以上の何か、あるいは実際に生の主体となる潜在的可能性を持つものとまことしやかにみなされる可能性が提示されることになる。もし現代の哲学者たち、特に還元的唯物論的見方をするものたちが議論するように、人間も十分複雑な複製法を用いることで完全に複製可能な生物学的基盤の中の電気パルスに過ぎないのであれば、我々が現在従事している純粋な生命の生物的生殖プロセスと、人工授精によりペトリ皿中で行われるもの、そして数学的アルゴリズムを基にしたアンドロイドの誕生を通した発展の結果に何らかの違いがあるだろうか?
アンドロイドが道徳的配慮の対象とみなされた場合、動物の場合と同様に、当然の帰結として議論の主題に挙がる実験の倫理についても考慮される。
もしこれがもっともらしいシナリオとして受け入れられるなら、問題は、これが道徳的に許容不能な実験のラインをまたぐのか、法的拘束の対象になるのか、ということになる。
そして、これらの懸念のわかりやすい例として、フランケンシュタインの物語が挙げられ
20世紀後半においては、モンスターが、どちらも特にプライベートや家族の生活についての権利を保護しているものである世界人権宣言(1948)、あるいは人権と基本的自由の保護のための条約(1953)
の下、法的救済が得られただろうと主張することはおかしなことではない。
別の可能な帰結として考慮されるのは、実験における同意の問題だ。第二次世界大戦の後に確立された、人体実験における10の規則を記したニュルンベルク綱領が引用される。
その一つ目で、こう明示されている:「被験者の自発的な同意が絶対に必要である。このことは、被験者が、同意を与える法的な能力を持つべきこと、圧力や詐欺、欺瞞、脅迫、陰謀、その他の隠された強制や威圧による干渉を少しも受けることなく、自由な選択権を行使することのできる状況に置かれるべきこと、よく理解し納得した上で意思決定を行えるように、関係する内容について十分な知識と理解力を有するべきことを意味している。後者の要件を満たすためには、被験者から肯定的な意思決定を受ける前に、実験の性質、期間、目的、実施の方法と手段、起こっても不思議ではないあらゆる不都合と危険性、実験に参加することによって生ずる可能性のある健康や人格への影響を、被験者に知らせる必要がある(Trials―, 1949)」
20世紀後半までは、重度の知的障害を持つものなどによって実験を行うことの制限は少なかった。
このラインをもう少し推し進めれば、動物の場合、より具体的には大型類人猿やイルカなどの哺乳類は、実験に関して現行法の下で厳密な制限を適用することができる。上で指摘したように、知覚をそのうちの単なる一つとする幅広い属性が、動物が道徳的配慮の適切な対象とみなされるに十分であると議論することができる。
となれば、アンドロイドをその議論から除外することも出来なくなるかもしれないということだ。
ラシャが投げかけたように、問いは「AI実験は、実験の目的(telos)が人の生産であると想定した途端から非道徳的だということになるのだろうか?」というものになる。著者は、次のような可能性も挙げている「自己反映的な意識やコミュニケーション可能な「人」を生み出すことを目標としたときAI実験は、一見して(prima facie)非道徳的である」(Lachat, 1986)。問いをわずかに変化させると、目的が人であることを要求するのではなく、目的が道徳的に重要な存在、すなわち、意識があるために権利を持つ存在であるかどうかを問うだけで十分だろうか? これは、実験をいくらか倫理的懸念の少ないものにするだろうか? もしこの問いへの答えが、終点が差異を生み出さないというもののなら、アンドロイドが動物と類似性のある形で扱われ、人間による実験から保護する目的の同様の制度の内に置かれない理由はない。
例えば、古典的快楽主義的功利主義の立場であれば、実験対象の苦痛の代わりに、他の大多数の功利が得られるなら正当化されるというかもしれないが、そもそもその立場自体が多くの批判にさらされていることは言うまでもない。また、古典的自然権理論からしても、アンドロイドが魂を持たない限り許されるだろう。しかし、アンドロイドが道徳的配慮にとって決定的であるという特徴を有する場合、アンドロイドも個人として内在的な権利を持つのではないだろうか、ということが議論される。そして
すると今度は、過去三十年に渡る中絶の問題を巻き込んだ議論と同様の議論に導かれるかもしれない。すなわち、もし最終生産物が権利を持つ存在であるなら、発展の連続性のどの時点で、その権利が付与されるのだろうか?というものである。動物の代理として議論すれば、アンドロイドが我々が意識と結びつける属性を示すという理由で、存在への利害を持っており道徳的重みを与えるに十分な利害を持つと言える。すると、それはそのウェルビーイングに影響するあらゆる議論について考慮されなければならず、もはや所有物とみなすことはできなくなる。
もちろん、これらの投機的な問いへの答えは哲学的な伝統に依るだろうと述べつつ、最後にこう記される。
科学者や工学者は、私が「科学的ヒュブリス」と呼ぶ戒め、すなわち、単に課題を遂行する技術的能力があるというだけで、それを作り上げなければならないという考えについて敏感でなければならない。
おわりに
以上が、論文からの抜粋である。アニマルライツを巡る議論の発展を見ることで、アンドロイドについての一つの有意味な見方が与えられることが議論されてきた。Conclusion(締め)では今後の発展によっては、ある種のアンドロイドへの扱いは、種差別の一形態とみなされるかもしれないことも指摘されている。
一方で、恐らく意識を獲得しているとは言えないだろうAIの著作権を巡る議論などはすでに顕在化しており、AIやアンドロイドを巡る道徳的議論や法的議論の盛り上がりは、アニマルライツの常識化を後押しすることにもなるだろう。
また、何より苦しみを経験しうる存在としてのアンドロイドの誕生は避けるべき悲劇であり、意識とは何か、権利が付与されるべき条件は何なのか、こういったことが明らかでないまま開発が続けられることで、予期しないタイミングで深刻な道徳的問題を発生させる可能性も十分ある。
よって、これらの議論は決して科学フィクションの世界の話でもなければ、遠い未来についての嗜好的思索でもないのであり、我々は、現時点からこういった議論を真剣に行っていかなければならないのだということを、改めて強調しておきたいと思う。
関連する書籍としてトーマス・メッツィンガーの『エゴ・トンネル 心の科学と「わたし」という謎 』を紹介したい。将来アンドロイドが経験しうるおぞまし苦しみと、それに繋がりうる研究の非道徳性について触れられている。
その他アンドロイドと道徳の問題について関連する議論は『人工知能、人工意識と道徳』参照