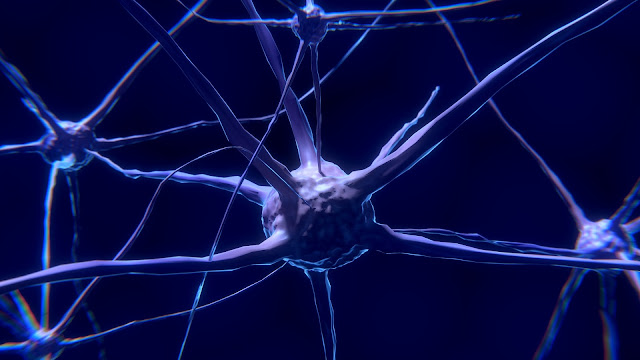倫理の自然化―オーウェン・フラナガン 他
倫理の自然化
オーウェン・フラナガン 他
Flanagan, Owen, Hagop Sarkissian, and David Wong. "Naturalizing ethics." Moral psychology 1 (2008): 1-26.
の簡単な要約。
Introduction
ここで扱われるのは
(1) 倫理が自然化されるべき理由
(2) 倫理が未だ自然化されていない理由
(3) ヒュームとムーアの二つの誤謬に対する弁護
(4) 規範倫理学は、多元相対主義にコミットする人類生態学の一部として最もよく理解できるということ
である。
広い意味での自然主義
自然主義とは、自然世界の一部としては理解できない存在や力を想定する超自然主義に相対するものを指す。そしてこれは、存在論的な意味についても、方法論的な意味についても言える。
なぜ倫理は自然化されていないのか
倫理が自然化されていないことには、米国や世界の他の多くの地域で、未だに宗教的影響が優勢であることが大きな原因の一つとしてある。しかし、神やそれに類する存在や力を信じるもっともな認識論的理由はないことは確かなので、それを考慮して話を進める必要はない…、というところに至るまでそれなりに説明がなされているが、日本ではそういった説明を要求されることはないほど比較的マシな状況であるため具体的に取り上げる必要はないだろう。
とはいえ、儒教や仏教のように、神秘主義的なものに基づいていない信仰もあることもある。特にブッダは、超自然的な存在論についてウィトゲンシュタイン(Wittgenstein)的な「語りえぬことについては、沈黙しなければならない」といった態度を貫いており、例え仏教的な教えに超自然的な記述が含まれていたとしても、ブッダの思想の本質的な部分はそれらを無視しても一貫した形で成立する。ちなみにフラナガンらがウィトゲンシュタイン主義者(Wittgensteinian)的と呼ぶブッダの態度は、日本語では「無記」と呼ばれる。
なぜ自然化なのか
自然主義的倫理は、上記のような超自然的存在論に反対する立場であり、二元論なども否定する。ただし、倫理的自然主義が主眼を置いているのは存在論ではなく、道徳的要請にアプローチするための適切な方法についてである。よって倫理的自然主義は、価値や規範を正当化するのに、超自然的な説明を行うことは拒絶する。しかしこれだけでは、倫理的自然主義の明確な像は浮かび上がってこない。
自然主義的倫理は、道徳的問いにアプローチするための、より具体的な方法論にコミットしている。その中でも主要なものが、道徳哲学は、概念的分析から自明かつ基本的な真理を導くア・プリオリな方法を認めない。自然主義的倫理では、実証的検証から逃れることはできず、また道徳科学は他の科学と連続的に繋がっていなければならないとする。
自然主義的倫理の特色をより理解するために、超自然主義的ではないが、自然主義的でもない倫理が考察される。具体的に挙げられる例がカント(Kant)の倫理理論である。カント倫理の内容は必ずしも超自然主義的なものではないが、神の存在を仮定することは倫理において必須のことであるとしていたし、意志や自由などの関連するいくつかの概念も、自然主義的には扱えない形而上学的なものであるとみなしていた。しかし、カントが想定していたような自由意志はそもそも存在しない。
とはいえ、人々が選択を行うことも事実である。そして
これらの活動やプロセスには現象論が存在する。人々が自分自身が選択をし、意図し、意志することを経験する。倫理は選択する人を見て、推論や検討や選択を含む自発的行為の鉱脈を見出すために、採掘の働きをすることが、フラナガンらの考える倫理の役割となる。つまり、「意志」や「自由」といった形而上学的概念の力を借りずとも、選択や自発的行為についての分析を行うことができる。この意味で、フラナガンはこの立場を「新両立主義(neocompatibilism)」という呼称を用いている。
道徳の理解
道徳の系譜学(genealogy of morals)は道徳的感覚、道徳的価値、道徳的規範などがどのように発生し、発展してきたのかを問う。文化人類学、学習の心理学、進化生物学などの組み合わせが道徳の系譜学で主要な役割を果たすだろうということは、自然主義的な哲学者の間である程度のコンセンサスがある。
規範倫理学は一方で、どのような徳、価値、規範、原則が個人や個人間のウェルビーイングや、調和に導くのかを決定し、弁護することに従事する。規範倫理には何が善で何が悪かについて語ることも含まれるが、倫理的自然主義者は、人間の必要や欲求や目的から導かれる基準を用いてそれらを評価する。
それらの一部は、例えば人間には平和、安全、交友関係、などが必要であるという我々の社会性動物としての性質によって固定されると考えられる。それらの必要の具体的な形態、つまりそれらが満たされる最良の形は、文化的に変化する要素を持つだろう。一部の目的や必要は、特定の文化のみに限定的で擁護可能な面が強い。よって道徳の目的は人間が必要とし、欲求することに部分として含まれる。
自然主義的認識論と規範性の問題
クワイン(Quine)は、自然化された認識論は心理学に吸収されたものであると議論し、多くのものはその議論を、認識論の規範的役割への反論として読みとった。そしてここでは、自然化された認識論に対する批判的指摘が紹介される。パトナム(Putnam)はクワインの自然化された認識論に対し「規範の消去は、精神的自殺の試みだ」と批判している。またジェグォン・キム(Jaegwon Kim)は「認識論から正当化が抜け落ちてしまえば、知識そのものが認識論から抜け落ちてしまう。我々の知識という概念は、それ自体が規範的な観念である正当化の概念と不可分につながっているからである」。と述べている。自然化された認識論の別の問題として、心理学は規範的な要素を含んでいないことに加え、記述的な部分も、実際には純粋に心理学的から来るものではなく、生物学、認知神経科学、社会学、人類学、歴史学などからの、幅広い情報を必要とするということも挙げられる。
自然主義的倫理と規範性の問題
クワインの考えをめぐるパトナムとキムの懸念は、ヒューム(Hume)のアプローチに対するカントの懸念に重ねられる。つまり、自然化された倫理からは、規範が抜け落ちてしまうと。しかし、フラナガンらは、自然主義的倫理を、自然化された認識論と同じように見るべきであると語る。
自然主義的倫理は、道徳的生活に関連する、ホモ・サピエンスが持つ共感やエゴイズムなどの能力や性質を特定し、人々がどのように感じ、考え、そして道徳的判断を行うのかなどを説明するものとなる。一方、自然主義的倫理の擁護者には、このような道徳心理学が倫理理論一般や、具体的には規範倫理の理解に寄与するのか? という問いが絶えず向けられる。
まず指摘されるのは、道徳的判断におけるこういった心理学的背景が倫理にとって重要であることは道徳哲学者の間でも一般的であるということである。そしてまた、「良いことを理解しているものはそれを行う」などの規範倫理に関連する倫理学の歴史上で馴染みある仮説は、検証可能であるということである。哲学的な心理学は検証可能な科学的心理学への道を与えており、それにより倫理学は、より優れた背景理論によって枠組みを作ることが可能になる。
こういった見込みにどんな問題があるだろうか?それについては続く節で考察される。
ヒュームの反論
しかし、誰もそのようなことを示唆してなどいない!どんな重要な道徳哲学者も、自然主義者も、非自然主義者も、単に適切な記述的真実を集めるだけで、完全な規範的倫理理論を生み出せるなどとは決して考えていない。道徳は単なる記述的な事柄だけでは極めて劣決定的(underdetermined)となる。しかし、それは科学や規範的認識論についても同じことである。それら三つすべては、拡張的(ampliative)な一般化と、劣決定的な規範に満ちた審理の領域である。拡張的な一般化とは、帰納法やアブダクションによって物事を一般化していくことを指しており、劣決定的であるとは、証拠や情報が不十分である中で、特定の結論を選択することなどを指す。つまり、一般的な科学においても、特定の信念を完全な証拠によって有無を言わせず決定することはできず、常に妥当と思われる推論と蓄積される証拠によって仮説の正当性を更新していくという手法が取られる。そしてそもそも、その妥当と思われる推論の基準もまた、それ自体科学的営みの内部では正当化できないいくつかの基本的な前提の上に成り立っている。ただし、もちろんこれは科学的根拠に基づく信念と、相対主義や非自然主義的信念を同質のものとみなすこととは違う。
ムーアの誤謬
続いて検討されるのが、ムーア(Moore)の自然主義的誤謬ついてである。つまり、「良さ」という概念は別の概念によって定義することはできず、それを行うとして、「___であることが良いことだ」と述べたとしても、「果たして___であるという意味で良いことは、良いことなのか?」と問いに対して開かれたままになってしまうため、そのような試みは常に誤りであるというものである。この議論に基づき、ムーアは「良さ」という概念は非自然的なものであると主張した。しかし、フラナガンらはまずこう指摘する:
自然化された倫理は還元的である必要はない。そのため、何らかの一元的な形で「良さ」を定義する必要もない。そして、そもそもムーアの前提にも問題があることが指摘される:
もしムーアが、ある定義がその適用についての必要十分条件を与えなければならないと考えていたのなら(彼は実際にそう考えていたように思われるが)、そのような定義が可能な場合には「問い」に対して「開かれた」状態にはならないということについて彼は正しい。しかし、一部の専門用語(例えば「偶数」や「奇数」など)や、特定の科学用語を除いて、その他のほとんどは適用のための必要十分条件を持たない。我々が「辞書的な定義」と呼ぶものは、現在の使用パターンと、機能的特徴づけの混ぜ合わせである。これは、自然言語のほとんどの用語は、何らかのプロトタイプ/イグザンプラー/ステレオタイプ構造を持っていることを考えれば意味が通る。G.E. ムーアが「良さ」の定義を見つけられなかったことは驚くべきことではない。「曖昧」や「椅子」という言葉の定義が見つけられないことが、曖昧さは非自然的な性質であるとか、椅子は非自然的な物体であるということを証明しないのと同じように、「良さ」の定義が見いだせないことは、良さが非自然的な性質であるということを証明するわけではない。また、道徳的な「良さ」を含め、「良さ」は一意的な用語ではないことも指摘される。
相対主義とニヒリズム
しかし、良さが一意的な用語ではないということから、それが極端な相対主義やニヒリズムに導かれるというのではないかという懸念が導かれる。これについてフラナガンらは以下のように答える:
自然主義的倫理はどのようにして極端な相対主義や、さらに悪い場合はニヒリズムに至ることを回避するのか? 答えは単純である。生物としての境界が、それらにとって何が良いのかということに制限を与える、ということである。
つまり、社会性動物であるホモ・サピエンスという種の一員である限り、個人についての事柄でも、個人間の事柄でも、何が良いことであるかについて多くの制約が自然と生じるということである。
自然主義的倫理の明確に規範的な部分は、なぜ一部の規範(規範の選択にかかわる規範も含む)、価値、そして徳は、他のものと比べて良いものであったり、より良いものであるのかを説明しなければならない。ある規範や規範の集まりを優位に見ることの一つの一般的な根拠づけは、それが我々の性質――我々の動物としての性質にしろ、社会的に位置付けられた存在としての性質にしろ――に属する一部の特性や能力を、改変し、抑制し、変換し、増幅するのに適しているということである。
...道徳は、どんな人間も要求する性質を持たないような振る舞いを例示化することを要求することできない。極端な相対主義はこれによって大きな制約を受ける。
これに関連して、自然主義的倫理の定言命法的な性質について説明される:
これは、道徳を仮言命法の体系に還元してしまうように思える。仮言命法とは、「もし、社会的協調を確実にしたいのならば、___をするべきである」といった特定の目的を確実にする望みに依存するものである。定言命法が、人間の利害や価値と独立ものであるとか、あるいはどんな場合であろうとも、あらゆる理性的存在を拘束するものと理解される限り、自然主義者が定言命法を可能なものとすることはできないというのは真実である。しかし、自然主義的倫理の目的が、ホモ・サピエンスという種の動機付けシステムに内在的なものである一方で、その種に属する特定の個人に対しては外在的なものである。これは、人類が与えられた性質と潜在性と共に探求できる良さの数は制限のあるものであり、それらの良さ(あるいは目的)は、仮言的条件に先行して置かれるものに制限を与える。これらの道徳論における事実を参照するにあたって、単純に任意の個人にあらかじめ存在する性質を指摘しているのではなく、むしろ、任意の個人の特定の性質を形成し導く助けとなる人類の性質に根付く基本的かつ根本的な理由を指し示しているのである。この意味で、それらは確かに「定言的」力を持つのである。
ニヒリズムについての懸念を取り払うのは容易である。単純にニヒリズムは現実に適用可能な選択ではないのだ:
ニヒリズムとは、何事もどうでもよい、という見方であるが、我々にとって物事は決してどうでもよくない。特定の生物種の一員であるために、そして歴史と共に社会的存在として進化してきた過程における特定の事柄のために、特定の物事には意味があるのである。現実はそのようなのである。
自然化された倫理:多元主義と人間生態学
デューイ(Dewey)の言葉「道徳科学は分離された分野の事柄ではない。それは、人間的な文脈に置かれた物理的、生物的、歴史的知識であり、その文脈において我々の活動を照らし導くものである」とともに締めの節に入る。
フラナガンらの主張の特色的な部分の一つ、倫理学が科学の文脈に位置付けられるのであれば、人類生態学の一部としてであろう、ということが語られる。
もし倫理学が何らかの科学のようなもの、あるいは何らかの科学の一部分となるとすれば、それは特定の自然環境や社会環境にある人類、人類集団、そして個人のウェルビーイングに何が寄与するのか、ということに関する人類生態学の一部としてであろう。何が良いか、ということは特定のコミュニティにとって何が良いかということに大いに依存する。しかし、そのコミュニティが他のコミュニティと相互作用するとき、これらの存在感が生まれる。さらには、良い行いや理想に見えるものが、歴史、人類学、心理学、哲学、そして文学からのあらゆる情報が考慮に入れられたとき、結局のところそれほど良いアイディアではないことが判明するということもありうる。もし倫理学が人類生態学の一部であるなら、実践と理想の評価に関する規範は、可能な限り広いものでなければならない。理想を評価するためには、今ここで、それらによって健康な人々と健康なコミュニティが促進されるかどうかを見るだけではいけない。この「健康」が、しばらくは気が付かないままでいられるが、人々を反映から遠のけ、結果的に毒された人間関係を導く、奴隷制、人種差別、性差別などの実践に関与することなくもたらされなければならない。そして、道徳の目的は多様であり、必ずしも個人やコミュニティにとって最も満足する帰結を創出するものではなく、その目的の一つとして、特定の生態学的ニッチの中で、この事実を最大活用することであること、また、多くの価値が持つ局所性と不確実性が、多様性や寛容さを生み出す重要な要素であることなどが語られ、最後に
多元相対主義者、プラグマティックな人類生態学者は、正しい態度を取っている。それは、有益なコミュニケーションや政治が、敬意や寛容さを要求するが、同時に悪を識別し、それに抗う能力を失いたくはないという世界において、そしてまた、共感的理解、判断における眼力、そして自己変化、場合によっては根本的な転身の能力の発展に関して、正しい態度である。と締めくくられる。