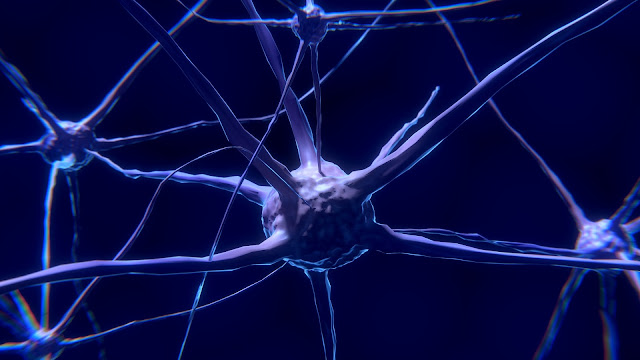現代ブッディズム:拒絶主義とエゴの消去
現代ブッディズム:拒絶主義とエゴの消去
Kei SingletonFirst published: 7. Apr. 2019;
Last updated: 7. Apr. 2019
このかりそめの身1にひとしい苦しみは存在しない。
形成せられる存在(=わが身)は最もひどい苦しみである。
―ゴータマ・ブッダ(ダンマパダ 202-203詩より)2
はじめに
このトピックは詳細まで議論しようとすれば、際限なく書き加えるべきことが増えてしまい、決して一ブログ記事で語れるようなものではない。 したがってここでは、節度のある分量内で、特に重要な点を概観することを目的とする。そのため、ブログ記事にふさわしい分量に調節するため、この記事を書くにあたって多くの部分を削った。より掘り下げた議論は、今後別の形で行っていくつもりである。
目次
1 導入:拒絶主義とは2 ブッダの思想
2.1 ブッダのスタンス
2.2 一切皆苦
2.2.1 トレッドミルを走る遺伝子の乗り物
2.2.2 悟りと存在バイアス
2.3 諸行無常
2.4 エゴを消し去る方法
3 エゴの現代理解
3.1 「エゴ」というミーム
3.2 瞑想研究
3.2.1 エゴの神経基底
3.2.2 条件付けによる学習
4 八正道が瞑想道ではない理由
4.1 誤った瞑想理解
4.2 「自己」抑制
5 エゴ理解の重要性
5.1 新たな種類のエゴと新たな種のアンチナタリズム
5.2 エゴイズムとエゴの死
6 おわりに
1 導入
この記事では、具体的な拒絶主義思想体系の一つとして、ゴータマ・ブッダの思想――宗教的な意味合いを持つ仏教と区別し、ブッディズムと呼ぶことにする――を取り上げる。 拒絶主義は、2014 年、社会学者ケン・コーツの著書『Anti-Natalism:Rejectionist Philosophy from Buddhism to Benatar』(Coates 2014) で導入された用語であり、私たち自身の存在に対して拒絶的な見方をする思想のことである。拒絶主義について彼はこう説明する。
[拒絶主義は] 生には、様々な形で、本質的かつ深い欠陥があることを見出す。なによりもまず、生は途方もない痛みや苦しみを課すものであること。第二に、それは自身の永続性を除けば、いかなる目的も意図もない完全に不必要なものであること。第三に、特に人類存在は、頼んだわけもなく、誕生や死、そして生まれ変わりという不必要なプロセスに徴兵され犠牲者となる無垢で知覚ある存在、すなわち子供に意識的に生を課すという点で、非難されるべきであるということである。動物たちを屠殺し食べ、他のあらゆる手段によって彼らを残酷行為の対象とすることもまた、人類存在の側面である。拒絶主義とは、これらの理由に基づく、存在に対する道徳的、形而上学的拒絶に関するものである。現代の世俗的拒絶主義の主要な意味内容は、生殖を自制することである。したがって拒絶主義の別の呼び名は、哲学的アンチナタリズムと言えるかもしれない。
つまり、拒絶主義とは、単に存在に対して否定的な考えではなく、それが必要もない一方で苦痛の多いものであること、あるいは他者にも苦痛をもたらすものであることという明確な理由を基に存在を否定的に考える立場であるということだ(引用中の「生まれ変わり」という言葉に引っかかった人もいるかもしれない。これは、拒絶主義はヒンドゥー教などの宗教思想にも見られるからである)。アンチナタリズムは実際には意味範囲が広く、道徳的理由による生殖の反対に限らないため、アンチナタリズムの文脈であえて拒絶主義という用語が用いられるのなら、その点を明確にした立場と理解すればよいだろう2。
しかし、コーツが与えている定義からすれば、拒絶主義はアンチナタリズムよりも広い意味と可能性を持ちうる。 その明確な例がブッディズムである。ブッディズムにはアンチナタリズムが含まれているだけではなく、ブッダはその拒絶主義的洞察から、既に存在を得た人が存在の負荷から解放される術も示しているのである。それによって、ブッディズムは拒絶主義思想の中でも特別に取り上げる価値があるものとなっている。
2 ブッダの思想
2.1 ブッダのスタンス
ブッダの思想の核心は明快である:一切は苦であり、どのようにしてそこから解放されるか。そのため、彼はバラモン教のような意味のない儀式や、苦しみの除去に関係のない哲学的議論などもすべて無用だと退けた。それだけでなく、確かめようのない死後の世界や魂についても沈黙したとも言われている。そういった疑問にこだわる人に、「毒の塗られた矢に射られた人が、その矢を抜き取って治療する前にそれを射た人がどんな人か事細かに議論していたら、そのうちに毒が回って死んでしまうだろう」と毒矢の喩えを用いて諭したという話はよく知られている。 ただし、他の自由思想家たちの中にも形而上学的問いについてブッダと同様の態度を取った思想家や、唯物論的な立場から明確にそのような概念を否定した思想家もおり、ブッダのみが際立って独創的だったというわけではなかった(三枝 2013)。また、ブッダはこれらの思想を頭ごなしに否定したわけではない。彼は実際にそれらを自ら体験し、意味がないと理解したものを切り捨てて言った末に、独自の思想を完成させたのだ。
2.2 一切皆苦
2.2.1 トレッドミルを走る遺伝子の乗り物彼のいう「苦」には、悲しみや痛みだけでなく、あらゆる苦悩や葛藤、嫉妬や退屈なども含まれる。思い通りにならないことのすべてと言ってもよい。人々は様々なことを求め努力するが、ほとんどの望みは叶わず、叶わぬ望みは嫉妬や妬みと変わり、苦悩や争いを生む。例え望みが叶ったとしても、過ぐに飽きが来て満足が持続することはない。この性質は、走っても走っても前に進むことはないトレッドミル(ルームランナー)になぞらえてヘドニック・トレッドミルと呼ばれる(ヘドニックは快楽についての、という意味)。ロバート・ライトは著書『Why Buddhism is True: The Science and Philosophy of Meditation and Enlightenment』(Wright 2017)で、進化心理学の観点から、これらの性質を説明している:
- これらの目標を達成することは、快楽をもたらさなければならない。なぜなら、ヒトを含む動物は快楽をもたらすものを追求する傾向があるためである。
- 快楽は永遠に続いてはならない。快楽が落ち着かなければ、私たちはそれを再び追い求めることはなくなってしまう。空腹が戻ってこなければ、最初のご飯が最後のご飯になってしまう。セックスについても同様だ。一度の性交の余韻の中で死ぬまで寝そべっていることになってしまう。これで多くの遺伝子を次世代に残せるわけがない!
- 動物の脳は1つ目のこと、すなわち快楽は目標の達成に伴うという事実に、2つ目の、快楽がすぐに消え去ってしまうという事実よりも焦点を当てないといけない。1つ目に焦点を当てれば、食べ物やセックスや社会的地位を心から追い求められるが、2つ目に焦点を当てた場合、葛藤を抱き始めるかもしれない。例えば、もし快楽が手に入れてもすぐに薄れてしまい、より強い渇望を残すだけのものだというのなら、そんなに一生懸命快楽を追求する意味とは一体何なのだろうと疑問に思うようになるかもしれない。それがわかるまでアンニュイな気持ちになってしまい、哲学を専攻していたらよかったとでも思うようになるだろう。
この説明には基本的な事実が前提とされている。その基本的な事実とは、「自然淘汰が関心を持つのは、遺伝子を次の世代に引き継ぐことだけ」ということである。 つまり、遺伝子にとって「私たち」は、自身のコピーを残すための「手段」、あるいはより具体的なイメージとして「乗り物」でしかなく、遺伝子の利益になるのなら、私たちの苦しみなどどうでもいいのである4。 これこそエフィリズムが、私たちの存在を支配するシステムが「根本的に破滅している」と強調する理由である。
ブッダが時代を超越して生物進化の理論や進化心理学の知識を持っていたなどということは当然ありえないが、これらの快楽についての性質は、生物進化の知識がなくとも経験的に理解できることだ。支配者一族の王子として生まれ、可能なあらゆる快楽を享受できる生活環境を与えられて育ったブッダは、自身の経験を通し特に確信をもって理解できたことだろう:
たとえ貨幣の雨を降らすとも、欲望の満足されることはない。「快楽の味は短くて苦痛である」(ダンマパダ 186詩)
と。
2.2.2 悟りと存在バイアス
苦の原因が欲求であることを見抜いたブッダは、その欲求の根源を探った。そして、諸々の欲望が生じる根本的な原因が存在への妄執であることを理解した。哲学者トーマス・メッツィンガーはこれと類似する概念を、より現代的な言葉で存在バイアス(existence bias)と呼んでいる(Metzinger 2017)。これは、私たちが自覚することもなく抱いている存在することは良いことであるという一種の偏見(バイアス)のことであり、何としても存在を確保するための行動に私たちを駆り立てる。そしてまた、このバイアスと表裏一体であるのが、「私」という感覚と、それに対する執着である。私たちは、「私」はあれが欲しい、これが欲しいと思い悩む。「私」はセックスをし、「私」は腹を満たさなければならないと生物学的に駆動される。そしてこれらの望みがかなわないことで、「私」は苦しい、という思いにさいなまれる。この根源にあるのが、「私」は満たされた形で生存を確保しなければならない、という観念である。
今と変わらず、生き物たちは絶えず葛藤し苦しんでいる。快楽はそれを鎮めるどころか状況を益々悪化させ、ひたすら悪循環を生じさせる。世界は苦しみに満ちている。ブッダはこの事実をありのままに見た。そしてそれらの苦の原因は、社会のありかたにあるのではなく、私たちの存在自体に由来するということを見抜いたのだ。あらゆることは私たちの存在それ自体の性質のために苦にたどり着く、それゆえ、一切の事柄は皆すべて苦、すなわち一切皆苦なのである。
2.3 諸行無常
例え多くの望みが叶えられ、富や喜びを貯えられたとしても、得たものからは執着が生じ、それを失うことの恐怖を呼び寄せる。誰も老いと死から逃れることはできず、必ずすべてを失うことになる。また老いや死それ自体が大きな苦であり、死に至る苦しみの前では富も快楽も権力も無力である。「私」が存在し、欲望に駆動されている間は、決して苦から逃れることはできない。
時間の流れと共に姿を変えていくこの性質は、生き物に限ったことではない。ブッダの観察の中で特に重要なものが、諸行無常と呼ばれるものである。これは、あらゆるものはたえず変化しており、時間の中に同一の実体を留めておくことはできないということを表す概念である。ブッダの最大の発見の一つは、妄執の原因である「自己」それ自体もまた無常なもの、つまり確固たる実体を持たないものだと見抜いたことである。自己という思いは、五感や記憶という時間と共に変化していく無常なものによって形成されるため、自己もまた無常なものであると。
苦の根源である「自己」には実体がなく、それはある種の「錯覚」であるということは、原理的にはこの錯覚に打ち勝つことができる可能性があるということである。心理学者スーザン・ブラックモアはブッダの洞察についてこう説明する:
彼は当時一般的だった宗教的教義を否定したが、その中には永遠の内的自我、すなわちアートマンが存在することも含まれていた。これに代わって、彼は人間の苦しみ、とりわけ自我という誤った観念への執着によって引き起こされると説いた。苦しみから抜け出す方法は、自我をたえず新たに作り出す欲求や執着をすべて捨て去ることである(Blackmore 2005)。
ブッダが悟った瞬間とは、この存在への妄執を滅して、生存への執着を断ち切り、「自己」という幻想を滅したときであると考えられる。ブッダは、そのまま苦にさいなまれることなく、完全な平安の中で静かに死を待つこともできた。そしておそらく、この境地に達し、悟ったまま真理を他者に語ることなく静かに死んでいった他のブッダも人類の歴史上に存在するのだろう。しかし、ゴータマ・ブッダは違った。彼は自らたどり着いた真理を教えを乞うものに伝えることで、その思想を世界に残した。
自己が錯覚であるとはどういう意味なのかと疑問に思う人もいるだろう。ここで「自己」の消失というときの「自己」とは、身体を含めた自分自身のことではないし、名前や他の社会的アイデンティティのことでもない。また、時間と共に変化していく個人という存在の本質的なアイデンティティを担保する何かについてでもない。したがって、自己が無常であるという指摘は、「個体」という単位が、道徳的に意味のないものであるという指摘を意味するわけでは決してない。例えば自己の同一性をめぐって、「今の私」と「次の瞬間の私」が同じものではないのなら、未来の私に対して、他者と同じように責任を持つのかといった議論があるが、ここでの話はそういった見方を支持するようなものではないということだ。そうではなく、ここでいう自己とは、「私」という感覚を指す。この場合の私という感覚を表す言葉として、自我、あるいはエゴという言葉があてられる。
2.4 エゴを消し去る方法
ブッダが特別に偉大である理由は、単に苦の根源を見抜いただけでなく、その根源を滅する具体的な術をも示したことにある。それにより、彼に思想は閉じた完全なものとなった。彼の思想の核心は以下の四つの認識にまとめられる:
- 苦諦(くたい):一切は苦であるということ。
- 集諦(じつたい):苦の原因は生存への妄執であるということ。
- 滅諦(めつたい):それを滅ぼせば苦から解放されることができるということ。
- 道諦(どうたい):それを滅ぼす方法があるということ。
この四つは合わせて四諦(したい)と呼ばれる。
四諦の四つ目の具体的な術は、八正道(はっしょうどう)(あるいは同じ読みで八聖道)と呼ばれる次の八つの教えにまとめられる:
- 正見(しょうけん):苦に関する(四諦についての)正しい見解を持つ。
- 正思(しょうし):欲を離れ、怒らず、他者を害さないという思いを持つ。
- 正語(しょうご):嘘や罵り、荒しい言葉や無駄口を絶つ。
- 正業(しょうごう):殺生、盗み、邪淫を絶つ。
- 正命(しょうみょう):理法に従った生活を営む。
- 正精進(しょうしょうじん):悪を滅し、善を促進するよう努める。
- 正念(しょうねん):一切皆苦、諸行無常など、あるがままの事実に正しく注意を向ける。
- 正定(しょうじょう):正しい集中を行う。
七つ目と八つ目はより具体的には瞑想の実践を指している。これらは互いに異なる種類の瞑想で、八つ目が精神統一を行うタイプの瞑想であるのに対し、七つ目は、現在マインドフルネスと呼ばれるものに分類される瞑想法と関係するものである。 マインドフルネスは集注の瞑想とは対照的に、その瞬間の経験に注意を集中させるものであり、エゴの消失に直接的に関係していると考えられている。しかし、残りの六つを含め、これら全体は一体のものであり、独立に考慮されるべきものではない。
3 エゴの現代理解
3.1 「エゴ」というミーム
信念や習慣やなどのアイディアは、人から人へ変化をしながら伝えられていく。その中には、非常に盛んに伝播されるものも、すぐに途絶えて消えてしまうものもある。これらのアイディアが、ある人の脳に受け入れられ、その人の行動(会話やネットへの投稿など)によって広められるかどうかは、例えばそれが何らかの意味で「正しい」考えであるかどうかには直接関係しない。そうでなはなく、あるアイディアが効果的に広められるかどうかは、それが属している人間の集団という環境に依存する。そのため、むしろ危機を煽ったり人々の願望と調和しやすかったりする宗教信仰や陰謀論などは、最も盛んに伝播される種類のアイディアとなる。元々大して関心を持たれなかったアイディアでも、人に伝えられる際に、意図的な理由のためであれ、記憶違いなどによる意図的でない理由のためであれ、「突然変異」を起こすことがあり、それが原因で非常に「人気な」アイディアに様変わりすることもある。これらの過程は、遺伝子が環境の中で競い合い、変化をしながら伝わっていく過程と同じであり、生物学者のリチャード・ドーキンスは、これらの模範によって伝わっていくアイディアの全てを指す言葉として「ミーム」という概念を導入した(Dawkins 1976)。
ドーキンスは初め、生物の遺伝子だけでなく、資源の限られた環境の中で競い合う自己複製子、すなわち自分のコピーを作るものは原理的にはどんなものでも5、すべて自然淘汰の法則に従うことを示す例としてミームを導入したのだが、その後一部の心理学者や哲学者たちは、ミームを私たちの意識や心の仕組みや成り立ちを説明する道具として拡張した。ミームは私たちの脳に感染し、自分たちのコピーを生み出すように私たちを仕向ける。また、それらは互いに親和的な集まりによって複合体を形成することもある。例えばブッダの教えというミームは、周辺宗教の信仰という別のミームと共生し、仏教というミーム複合体の一部として伝播されたことで、現代まで広く伝わることになったということも考えられる。
ミームという新たな自己複製子を導入する利点は、私たちの持つどんな形質を選んでも、私たちがそれを持つ理由はすべて、究極的には遺伝子の利益に帰せられるという見方から解放される助けになることだ。鍵となるのは、遺伝子の乗り物である私たちは、ミームの乗り物でもあり、それらの異なる自己複製子は互いに利益を巡って競合するという見方である。例えば、ドーキンスが述べる「独身主義の習慣などは、おそらく遺伝によって伝わるものではあるまい。…特殊な状況を除けば、独身主義を発現させる遺伝子は、遺伝子プール中での失敗を運命づけられているからだ。しかし、独身主義の「ミーム」には、ミーム・プールの中で成功しうる可能性がある」(Dawkins 1976)。 と言った例は理解しやすい。これと同様の見方をすれば、アンチナタリズムの弱みとして、その思想を持つ人が子供を作らないため、アンチナタリズムは広まらない、というしばしば見かける批判が正当なものではないことだと分かるだろう。気質や家庭環境によって決まる傾向性は確かにあるだろが、思想自体は遺伝するものではないし、十分強力なミームは遺伝子にも打ち勝つことができる。
スーザン・ブラックモアは、「私たちが」ミームを扱っているのではなく、「私たち」という感覚、すなわちエゴ自体が、一種のミーム複合体――彼女はそれを「自己複合体」と呼ぶ――なのではないかという考えを提唱している(Blackmore 1999):
…信念、意見、所有物、個人的な好みはすべて、それらの背後に信じる者あるいは所有者がいるという考えを補強しているということである。あなたが一方の陣営を支持し、かかわりをもち、事件の弁護をし、あなたの所有物を守り、そして強い意見をもつということをするほど、あなたはことばを語る一人の人間(体と脳)だけでなく、信念と呼ばれる深遠なものを備えた内なる自己も存在するという偽りの考えを強化していく。
…結論として、自己複合体が成功しているのは、それが真実だからでも優れているからでも、美しいからでもない。それらが私たちの遺伝子を助けるからでもないし、私たちを幸福にするからでもない。それが成功するのは、その内部に入り込んだミームが私たち(伸びきった情けない身体的システム)を彼らの増殖のために働くよう説得するからである。
つまり、エゴが存在するのは、「私たち自身」のためでもないことはもとより、遺伝子の利益のためでもなく、他ならぬミームにとって利益となるからであるという見方である。デネットも同様の見方を主張している、「私たちのお話は紡ぎ出されるものであるが、概して言えば、私たちがお話を紡ぎ出すのではない。逆に、私たちのお話の方が、私たちを紡ぎ出すのである。私たち人間の意識は、そしてまた私たちの物語的自己性は、私たちのお話の所産ではあっても、私たちのお話の源泉ではないのである」(Dennett 1991)。
しかし、ブラックモアとデネットの見方には違いもある。一つはブラックモアがエゴをミーム複合体であると見ているのに対し、デネットは意識それ自体がミーム複合体であると考えていることだ。ブラックモアがデネットのこの見解に異論を示すのは、まさに瞑想やサイケデリックドラッグにより、意識的でありながらエゴを消し去ることが可能だからである。そしてもう一つ重要な違いは、デネットはエゴを「良性」の錯覚であるとみなしているのに対し、ブラックモアはエゴが苦しみの源泉であり、決して好ましいものではないと、少なくとも部分的に理解していることにある。それらを踏まえ、ブラックモアは瞑想を通した意識研究に期待を示している:
瞑想を実践している科学者や、科学研究を行っている瞑想家はすでにいる。ここからつぎのような期待が生まれてくる、すなわち、科学と個人的な実践がいつか一緒になって、私たちに明瞭な洞察を与えてくれるのではなかろうか。そのときには、意識の錯覚を捨て去り、自己と他者の錯覚を見抜けるようになり、私たちにはただ一つの世界が開かれる(Blackmore 2005)。
だが、なぜ瞑想によってエゴを消し去ることができるのか、という疑問は残る。瞑想によってエゴを滅するということは、ブッディズムの中でこの部分が唯一確信を持つのが難い部分である。だが、以下の節で示すように、近年の科学研究により、瞑想を含め、ある種の条件下でエゴの消失、あるいはエゴの死(ego death)が起こることは確認されており、ブッディズムの正当性が完全に確証され始めている。そしてそのメカニズムを含めて深い理解が得られれば、鍛錬の必要な瞑想よりももっと簡単な方法で誰もが苦から解放されることも可能になるかもしれない。仏教学者の佐々木閑氏はまさにこのことを語っている:
釈尊が目指したのは、他の人たちに自分の体験を伝え、同じ方法で精神の向上を成功させることであった。その方法に、理屈を越えた説明不能な部分があったため、「まずは私を信頼せよ」と言って人々を誘った。そこに仏教の宗教性があったのだが、そのような宗教性は別になくても構わないのだ。精神向上のためのシステム全体が合理的に説明可能であるならそれに超したことはない。…自分の体験が、合理性に基づいた科学的真理として皆に承認され、多くの人たちが当然のこととして、そのシステムを利用する、これこそ仏陀の本懐ではないか(佐々木 2006)。
3.2 瞑想研究
3.2.1 エゴの神経基底近年の研究で明らかになっているのが、ある種の瞑想によって、デフォルトモードネットワーク(DMN)と呼ばれる脳のネットワークに著しい影響を及ぼすことができるということだ。DMNのサブ領域である後帯状皮質(PCC)は、記憶を想起したり、未来についての考えを巡らせることを含め、自己言及を行うプロセスにおいて重要な役割を担っているいる。そして瞑想、あるいは部分的に同様の影響を持つサイケデリックドラッグの研究によって、これらの部位の接続の低下と、自己の消失に明かな相関があることが示されいている(Brewer et al. 2013, Brewer and Garrison 2014)。
目をつむって何も考えないことを実践してみようとすればわかると思うが、私たちの頭の中は絶えずとりとめもない思考が渦巻いている。この思考にによって語り手的な自己が生み出されるという事実は、ブッダの洞察や、より現代的なミームという概念を用いた記述に適切に対応している。サイケデリックドラッグの研究については『サイケデリックドラッグとEgo Death』を参照
3.2.2条件付けによる学習
この語り手的な自己形成のメカニズムについて、もう少し詳しい洞察も行われている。例えば
以前に経験した楽しみと苦しみを擲(なげう)ち、また快さと憂いとを擲って、清らかな平静と安らいとを得て、犀の角のようにただ独り歩め。(スッタニパータ 67詩)
のように、ブッダは経験される快苦は幻であり、心を奪われてはいけないということを強調したが、ブリュワーらは、ブッディズムにおけるこのストレスモデルは、行動心理学におけるオペラント条件付けという理論と重なると考えている(Brewer and Garrison 2013)。 オペラント条件付けとは「有機体は、記憶を並べ、X(例えばセックス)を快的な、Y(例えばショック)を不快な感覚に結び付けることで、振る舞いを学び、そして強化する」。と説明されるプロセスのことである。そして、ブリュワーらはさらに重要な指摘として、こう述べる:「人間の場合、主体の感覚が与えられたとき、この関係づけの学習プロセスは、「私」がセックスをしているとか、「私」がショックを受けている、といった、行為の背後にある誰かにプロセスを帰属させる自己言及的な記憶のエンコードを含む」。このループをミームという概念を用いて記述したものが、ブラックモアの自己複合体の理論に他ならない。そして、このオペラント条件付けのループを通してエゴが形成される過程に、PCCが深く関与していることが強く疑われており、エゴの形成を担う部位の絞り込みが始まっているといえるかもしれないという期待が広まっている。
4 八正道が瞑想道ではない理由
4.1 誤った瞑想理解
エゴを実際に消失させられることは、科学的な裏付けを持って示され始めていることがわかった。しかし、LSDは60年代のヒッピーたちをブッダにしなかったし、現在も世界中で瞑想が実践されながらも、誰もがブッダにはなっていない。エゴの(一時的な)消失だけでは、解脱の十分な条件にはならないのだ。 近年、瞑想は様々な動機から注目され、すでに商売人たちの釣り餌として利用されている。彼らの釣り糸から過大な広告と共にぶら下がっているそれは、ブッディズムで語られる瞑想とは全く異なる。近年行われた研究(Gebauer et al. 2018)はそれを示す典型的な例だろう。この研究では、瞑想やヨガを行った後、人々のエゴは抑制されるどころか、むしろ強化されるということが示唆されている。彼らの研究の内容は、なんらかの「スキル(技能)」の鍛錬をした場合、自己強化が行われることが一般に示されており、瞑想やヨガの鍛錬でも同様のことが予測されるが、Facebookでヨガや瞑想教室の参加者を集めて調べたら実際にそれが確認されたというものだ。ただし、彼らが取った手法は、脳イメージングなどによる測定ではなく、自己肯定感などを測るための問いを評価させるというものである。
いずれにしても、この研究結果は驚くに値しないし、ブッディズムにおけるエゴ消失の手段としての瞑想の正当性を揺るがすものでもない。なぜなら彼らの瞑想の理解が根本的に間違っているからだ。このような誤った瞑想の認識は珍しいことではなく、ファッション的な広まりのもたらす結果は初めから目に見えている。エゴを滅するための「正しい」意味での瞑想とは何か、それを説明する現代的な言葉を求めるのなら、ジッドゥ・クリシュナムルティの言葉を参照する以上の選択はない6。彼はこう説明する:
瞑想は思考のパターンに自我を包ませることでも、快美な経験な体験に身を任せることでもない。瞑想は始めを持たず、それゆえ終わりがない。「今日から思考を制御し、静かに瞑想の姿勢を取り、調息をはじめよう」というとき、あなたは自己欺瞞の陥穽にはまったのである。何か途方もない思念やイメージに没入することによって、ちょうど子どもがしばらくは玩具に夢中になるように、しばらくは自我を静めることはできるであろう。しかしそれは瞑想ではない。子どもはその玩具にあきるとまた前のように騒々しく、いたずらになる。瞑想は何か見えない道をたどって、何か空想的な至福を実現することでもない(Krishnamurti 1970)。
ファッションや健康を「目的」とする瞑想が、この意味での瞑想とかけ離れているということは明らかだろう。クリシュナムルティさらに、「では、エゴから解放されるための方法はどういうものか」、という問いに対してこうも答えている:
あなたは自我を解放できない。あなた自身がこの不幸の根源である以上、<自我>を滅する<方法>を求めていては、ほかならぬ自我の滅却過程であなたは別の<自我>を作り上げてしまうであろう。
先ほどのオペラント条件付けの言葉を用いて表現すれば、エゴを一時的に消し去った達成感によって条件付けのループが起こり、エゴが強化されるといえる。ブッダの教えで徹底されていることは、苦からの解放――すなわちエゴからの解放――さえも、究極的には渇望してはならず、得られた真理にさえ執着してはならない、というものだ。エゴから解放される方法として瞑想があるが、それをエゴから解放される方法として用いエゴからの解放を欲求しているうちは、エゴから解放されることはできない。そして、存在の解放に至る道で得たものに執着してもならないのだ。ブッダは鍛錬における心得として次のように述べている:
この身体は水瓶のように脆いものだと知って、この心を城郭のように(堅固に)安立して、智慧の武器をもって、悪魔と戦え。勝ち得たものを守れ。____しかもそれに執着することなく(ダンマパダ 40)。
歩みを進めても、その進歩に執着を見せるたびに、私たちはエゴの「輪廻」に引き戻される。クリシュナムルティはこうも残している、「真理とは、そこに至る道のない土地のである」と。少なくとも八正道は、自己満足に繋げるための習い事として行うようなものではない。しかし、改めて、エゴの神経科学的理解とそれを制御する技術が発展させられれば、真理に至るために、必ずしも八正道を徒歩でたどって向かう必要はなくなる。
4.2 「自己」抑制
また、重要なのは苦について(四諦について)の正しい認識だけではない。八正道にある正しい思いや言葉遣い、あるいは正しい行いについての記述などは単に道徳的戒律として含まれているのではない。煩悩や怒り、争いや不正は直接に自分自身の苦を生成するだけでなく、エゴを強化することにもなるためだ。例えばロバート・ライトは憎しみについて進化心理学的観点からこう記述している:
もし誰かに対する憎しみの感情を観察し、ただその感情だけを観察し続けたなら、その感情は、例えば、その人があなたの憎しみを買うために行った行為への復讐を行うことを想像させるなど、あなたがもしそのような観察をしなければしただろうことをしなくなる。もしあなたが実際にこの復讐のファンタジーに浸っていたなら、それは快感をもたらしたのではないだろうか?宿敵に降りかかる恐ろしい運命を想像するより愉快なことがあろうか?これが快感である理由は、おそらくこのこと、すなわちライバルを転覆させ敵を害することは、自然淘汰がそのモジュールをあなたを駆り立てるために設計したものだからだ。よって、自然淘汰の観点からみれば、そのモジュールはあなたを復讐のファンタジーに浸らせるミッションを完了することで、報酬を引き出すに値するものとなる。そしてこの報酬は、次の機会においてそのモジュールをさらに強化することになる。
つまり、憎しみのパターンもまた、オペラント条件付けのループを通して学習され、それに伴ってエゴ自体も強化されてしまうのだ。
5 エゴ理解の重要性
エゴを取り去ることができるのなら、エゴや意識そのものが何であるかということについての正確な理解は必要ない。毒矢の治療を行うのに、毒矢についての全てを知る必要はないからだ。とはいえ、目的をエゴを効果的に消し去ることに限定しても、エゴや意識そのものに関する私たちの理解はまだ十分とは言えない。加えて、エゴについてのより深い理解は、個人の枠を超えたエゴの問題の解決、あるいは回避にもつながりうる。
5.1 新たな種類のエゴと新たな種のアンチナタリズム
メッツィンガーは、エゴを持つ存在を総称して「エゴマシーン」と呼んでいる(Meztinger 2009)。これは単にエゴを持つ動物を指すだけではない。エゴを持ちうる存在は動物に限らないからである。人工知能の開発が進めば、やがて人工意識が生み出される可能性もある。人工知能は苦しみを回避し取り除くための非常に強力な「道具」になる可能性を秘めているが、同時にそれ自体が苦しむ存在になってしまう可能性もあるのだ。そのような存在になったときは、もはや彼らを道具として扱うことは許されない。そして人々が仮にそのことを理解したとしても、もっと恐ろしいシナリオは、彼らが意識やエゴを持っていることに私たちが気づかないでいることである。
意識という現象のメカニズム全体を解明するのにはまだ長い時間がかかるかもしれないが、少なくともヒトの脳内でエゴが生み出されるのに必要な条件が部分的にでも理解できたなら、人工知能の開発の過程で、人工的なエゴマシーンを生み出してしまうリスクを減少させることにもつなげられる。エゴについて理解することが重要である理由は、新たな種類のエゴマシーンの出現を回避するためでもあるのだ。このトピックについては『人工知能、人工意識と道徳』の項を参照。
5.2 エゴイズムとエゴの死
私たちの存在の由来である、唯物論的な進化的歴史と自己の非実在性が明かされてきたが、メッツィンガーはこの流れの延長として、もう一つ別の懸念を示す。それは以下のような状況が導かれることである:
一つのありそうな筋書きは、長年の間、繰り返し問われてきた問題、例えば自己の本性や意志の自由、心と脳の関係、あるいは人格を人格とするものは何かといった問題を神経科学者と哲学者が解決するよりもずっと前に、通俗的な唯物論が定着してしまうことだろう。「脳の専門家や意識の哲学者連中が何を言っているかわからないが、結論ははっきりしていると思う。もうバレているんだ。自分たちは遺伝子を複製するバイオ・ロボットで、冷たく空しい物理的宇宙にある孤独な惑星のこの場所で生きている。脳をもっているが、不死の魂はもっていない。七十年かそこらが過ぎれば、幕が落ちる。死後の世界などないし、誰に対しても褒美もなければ罰もない。究極的には、誰もが一人きり。私はこのメッセージを理解したので、あなたは、私がそれに合わせて振る舞いを変えると信じたほうがよい。私が策略を見通したことを誰にも知らせないほうが、もしかしたら賢明だろう。一番効果的な戦略は、私は保守的で、道徳的価値を信じている古いタイプの人のふりをし続けることだろう」といった具合に。
この懸念は非常にもっともなものだろう。自然科学をかじったもの、あるいはその中の何らかの分野に専門的に携わってはいるが、極めて(精神的な意味で)閉鎖的に生きてきた人々の中には、まさにこのままの「通俗的な(vulgar)唯物論」を信奉するものがいる。
しかしもちろん、彼らのその「信念」は正しいものではない。例えばそういう類の人々がお気に入りのニヒリズム、すなわちこの世界にはいかなる価値も存在しないという見方は、特に彼らがそれを引き合いに出す文脈においては、これまで散々具体例を見てきたように、私たち自身がその価値判断の機能によって駆動される存在であるという自然科学的知識によって退けられる。そうなると次に彼らが選択するオプションは、エゴイズム(利己主義)、すなわち「自己」の利益を追求することにのみ価値があるとみなす立場である。
もちろん、引用したシナリオ中のセリフにもある通り、多くの場合この種の人たちも、社会通念という程度のレベルのものでこそあれ、表面上は何らかの道徳規範に従う。それが自己の利益から損害を差し引いたもののを安定的に保つ「戦略」だからだ。しかしこのような人にとっては、他者を工業的に搾取したり他者に苦痛の伴う存在を強制することを正当化するのに、「それが社会的に受容されている」という事実さえあれば十分である(こう考えてみれば、メッツィンガーの懸念はなんてことない、既に少なくともその一部は現実のものであるとも言えるかもしれない)。
しかし、この懸念は、メッツィンガー自身が関心を向ける「どの意識状態が私たちにとって有益で、どの意識状態が有害なのか」という問い、そして彼が提案する意識倫理学、すなわち「よい意識状態とはどのようなものか」という問いを通して、反対の見方も示せるのではないかと思う。つまり、個人にとっての最大の利益がエゴから解放されることであるなら、自己の利益を追求するということは、結果的に己の振る舞いを制して欲望を捨て去ることになり、利己主義の観点からでさえ、ブッディズムこそが「正しい」選択だと示されることになるからである。また、神経科学によるエゴ理解が進み、エゴ――したがってエゴイスティックな振る舞い――を消し去る効果的方法が示されれば、エゴイズムさえ益々脅威ではなくなる。また、この境地においては、メタ倫理学におけるis/ought to問題さえ、もはやほとんどの場合障害とならない。「おそらく真の道徳性の大部分は、何か偉大で高貴な行為を引き受けることよりもむしろ、単純に私たちがふつうにしている有害な行為、つまり自己という偽りの感覚をもつことに由来する有害な行為をすべて止めることだろう」(Blackmore 1999)というブラックモアの洞察は的を射たものだろう。
ここで改めて示されることは、第一に重要なことは、八正道の中で一番初めに挙げられている正見、すなわち存在は苦であり、その存在の負荷から解放されることが私たちにとって最良のことであるという事実を、人々が正しく認識することである。存在バイアスを含めた種々なバイアスを拭い去り、あるがままの事実に向き合うことこそ、倫理的問題の解決に向けた第一歩であるのだ。自然科学と調和し、解決するよりも多くの問題を生じさせることなく倫理学の抱える難題を解決し、一貫して閉じた倫理体系を示せるのは、拒絶主義としてのブッディズムだけである。
6 おわりに
最後にいくつか強調しておかなければならないことがある。一つは、ブッディズムはあくまで各「個人」が存在の負荷から解放されるための手段を示したものであり、他者を苦から救うことについては何も述べていないということである。ブッディズムについて伝えることはその一つの可能性になるとはいえ、存在の欠陥に向き合おうとしないものにとってはなんの救いにもならない。それ自体は問題ではないかもしれないが、無視できない問題は、その帰結として一方的な他者への加害をやめようとしない人たちの存在である。 目の前で暴力が行われており、自分がそれに介入することで、その暴力の被害者を救いうる可能性があるのなら、それこそ、ただ「仏面」をして、聞く耳を持たない相手に非暴力を訴えることは正しい選択とはならないだろう。ブッダは論争を避け、怒りを滅するよう説いた。しかし先にの述べたように、これはエゴを強化し、「自身」にとって不利益になるからであって、決してブッダが相対主義、すなわち物事の真偽や善悪は人それぞれであるという立場を取ったからというわけではない。 論争を含めた他者を救うための抗議行動は、その点においてブッディズムに反するものではない。
二つ目は、エゴが思考を行うのではなく、思考がエゴを形成するのだという構造を理解するツールとしてミームという概念を導入したが、ミームを用いたエゴの記述に気を付けなければならないことがあるということだ。エゴだけではなく、意識そのものに言語や文化が重要な役割を果たしていると考えるデネットとは対照的に、ブラックモアは意識自体がミーム複合体だという立場は支持しないが、それでももし、エゴが完全に自己複合体によって説明されるとすれば、ヒトでない動物の大半は模範という習慣を持たず、したがってミームを持たないため、エゴも持たないことになる。 その場合、本章を通して見てきた考察の通り、彼らは通常の意味で苦しみを経験しないということになる。 もちろん、実際に動物たちは苦しみを経験するエゴを持たないという可能性も排除できない。その場合、苦しみとはホモ・サピエンスというたちの悪い猿と他の少数の種に属する個体に固有のものだということになり、私たちが存在すると考えている問題の大半は、実は存在しないということになる。 しかしこれは、蓄積されてきた動物の主観的経験に関する研究結果が示唆することに反する。また近年の瞑想やサイケデリックドラッグの研究が示唆しているのは、自己は消去可能なものである一方で、それは単なる語り手的自己以上の複雑な機能であり、一言にエゴといっても、複数の部分や階層があるということである(Letheby and Gerrans 2017, Millière et al. 2018)。ここに自己複合体によるモデルの限界があるかもしれない7。
いずれにしても道徳的に重要なことは、err on the side of caution(充分すぎるくらい慎重になるべし)の原理に従うことだ。 すなわち、私たちがヒトでない動物たちに私たちと同様の苦しみを経験する能力があると想定して振る舞った場合、仮にそれが間違いだと判明しても大きな損害を被るものはいないが、彼らに苦しみを経験する能力があるという可能性を無視して振る舞った場合、実際に彼らが苦しむということが事実であったとき、私たちは彼らに取り返しのつかない損害を与えてしまうことになる。
ヒトでない動物の意識やエゴの有無や性質については個別に論じる必要性のある重要なテーマであり、これ以上は立ち入らないことにするが、それらについての慎重な見方が正しいとすれば、ヒトでない動物の苦しみは最も優先されるべき問題となる。各個人の経験する苦しみはそれぞれ無視できるものでは決してないが、「もしも」その総量を基準に考えるのなら、ヒトが経験する苦しみは、ヒトでない動物が経験していると考えられる苦しみに比べれば全く取るに足らない程度のものになると推測される。これは、もし仮に、人間誰もが存在の負荷から解放されることができるようになり、人類世界から苦しみが取り除かれたとしても、この地球上の問題の大半は残されたままになるということを意味している。 メッツィンガーそのことについて的確にこう述べている:
もしこの惑星の73億の人間がビーガンのブッダになったとしても、野生動物の苦しみという問題が残されている。我々は依然として、超知性でさえ解放することが出来ないかもしれない、自己意識を持つ生物の苦しみの海に囲まれたままになるのだ(Meztinger 2017)。
エゴの死による存在の負荷からの解放という手段が、追求していく価値のあるアプローチの一つであることは間違いない。しかしそれは、世界全体に存在する問題のほんの一部を解決するものでしかない。私たちは同時に、問題の他の部分を解決する手段も検討していかなければならないのだ。最後に、もう一つブッダの言葉を引用してこの章を締めたいと思う:
一切の生きとし生けるものは、幸福であれ、安穏であれ8、安楽であれ。(スッタニパータ 145詩)
――――――――
1. 参考文献の訳注では、かりそめの身は「われわれの変化する生存の諸要素の集合、個人存在をいう。」と説明されている。
2. 本章を通して、ダンマパダからの引用は(中村 1978)、スッタニパータからの引用は(中村 1984)を参考文献とする。
3. ちなみに、現在日本では、おおまかではあるが、この拒絶主義の意味合いに対応してアンチナタリズムという用語が用いられ、倫理的な基盤を持たない立場に対応して反出生主義という用語が用いられていると思われる。日本語でも正確には拒絶主義という用語を用いるべきかもしれないが、英語圏でもrejectionsism という用語はそれほど広まっておらず、基本的にはantinatalism を道徳的アンチナタリズムと理解すべきだという考えが多数派であるように思えるため、今後のこの使い分けが維持されるならば、あえて拒絶主義という用語を積極的に導入する必要はないと考えられる。
4. 念のために、遺伝子には意志も意識的な目的もなく、利益とはメタファーであるということを注意しておく。
5. コピーにはミスが起こる可能性があるという条件も含まれなければいけないが、永久に100%の精度でコピーを生み出し続けられるものは現実には存在しない。
6. クリシュナムルティ自身はブッディストではなく、いかなる哲学的見解もドグマも徹底して退けた。しかしその精神の自由さを含め、その見解の大部分はブッディズムの示すことと重なる。
7. ヒトでない動物のエゴに関するブラックモア自身の考察は、例えば(Blackmore 2003, 2018)を参照。
8. 参考文献の脚注:恐怖もなく、危害を加えられることもない、の意。
参考文献
- Blackmore, S. (1999). The Meme Machine. Oxford University Press.
―― (2002)ミームマシーンとしての私(上・下). 垂水 雄二 訳, 草思社. - Blackmore, S. (2003). Consciousness: an introduction. Oxford University Press.
- Blackmore, S. (2005). Consciousness: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
―― (2010). 意識. 信原幸弘 他 訳 岩波書店. - Blackmore, S. (2018). Are Humans the Only Conscious Animal? Decoding the puzzle of human consciousness. Scientific American https://www.scientificamerican.com/article/are-humans-the-only-conscious-animal/.
- Brewer, J., Garrison, J. and Whitfield-Gabrieli, S. (2013). What about the “self” is processed in the posterior cingulate cortex?. Frontiers in human neuroscience 647.
- Brewer, J. and Garrison, K. (2014). The posterior cingulate cortex as a plausible mechanistic target of meditation: findings from neuroimaging. Annals of the New York Academy of Sciences 1307.1, 19-27.
- Coates. K. (2014). Anti-natalism: Rejectionist philosophy from Buddhism to Benatar. First Edition Design Pub.
- Dawkins, R. (1976). The Selfish Gene. Oxford University Press.
――(1991). 利己的な遺伝子. 日高敏隆 他 訳. .紀伊國屋書. - Dennett, D. C. (1991). Consciousness explained. Boston, MA: Little, Brown and Company.
―― (1998) 解明される意識. 山口泰司 訳. 青土社. - Krishnamurti, J. (1970) The only revolution. London: Gollancz.
―― (1982) クリシュナムルティの瞑想録―自由への飛翔. 大野純一 訳. 平河出版社. - Letheby, C. and Gerrans, P. (2017). Self unbound: ego dissolution in psychedelic experience. Neuroscience of consciousness 2017(1).
- Metzinger, T. (2009). The Ego Tunnel: The Science of the Mind and the Myth of the Self. Basic Books.
―― (2015) エゴ・トンネル―心の科学と「わたし」という謎. 原塑, 鹿野祐介 訳. 岩波書店. - Metzinger, T. (2013). Two principles for robot ethics. In E. Hilgendorf and J.-P. G\"{u}nther (eds.), Robotik und Gesetzgebung. Baden-Baden: Nomos.
- Metzinger, T. (2016). Suffering. In Kurt Almqvist and Anders Haag (eds.), The Return of Consciousness. Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.
- Metzinger, T. (2017). Benevolent Artificial Anti-Natalism (BAAN). Edge Essay. https://www.edge.org/conversation/thomas_metzinger-benevolent-artificial-anti-natalism-baan.
- Millière, R., et al. (2018). Psychedelics, meditation, and self-consciousness. Frontiers in psychology 9:1475.
- 中村元. (1978). ブッダの真理のことば, 感興のことば. 岩波書店.
- 中村元. (1984). ブッダのことば―スッタニパータ. 岩波書店.
- 三枝充悳. (2013). インド仏教思想史. 講談社, .
- 佐々木閑. (2006). 犀の角たち. 大蔵出版.
- Wright, R. (2017).Why Buddhism is true: The science and philosophy of meditation and enlightenment. Simon and Schuster.